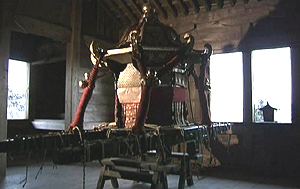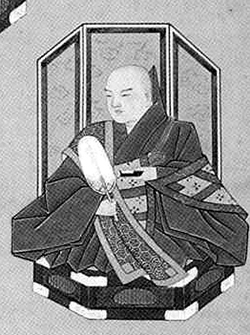| 1.「願立」の基本要素
延慶本、覚一本、四部本、長門本、源平盛衰記の諸本を比較すると、物語の展開上必ず含まれている要素が存在する。この要素分析は山下宏明氏のすぐれた研究があるが、それをベースとして、私なりにアレンジしてみた。この要素が「願立」成立の基本要素と言うことができるだろう。 「願立」成立の基本要素 ① 起 :師通病死事件のきっかけとなる円應殺害事件の発生 ② 承 :山門大衆の強訴と師通の指示による禰宜射殺事件の発生 ③ 展1:禰宜射殺に怒った山門大衆の呪詛 ④ 展2:山王権現のたたりの発生 ⑤ 結 :母北の政所の願立、師通病死 屋代本は読み本系の古本とされているが、ほとんどこの基本要素の①~⑤だけで構成されており、この5つの基本要素が物語成立の最小限の構成要素であることを示している。屋代本の⑤に若干の北の政所の立願内容を具体的に加えたのが四部合戦状本と位置づけることができる。四部本の概要を示すと次のような展開となる。 ①~③ 基本要素通り ④ 山王のたたりの発生、大殿・北の政所は身をやつして ⑤-1 北の政所の三つの心中の立願(回廊造進、小袖の寄進、 ⑤-2 出羽の童神子に十禅師が乗り移り、三つの心中の立願を ⑤-3 関白師通薨去 ⑥ 基本要素外―腫れ物が巨大で納棺できない。 ⑥の部分は別に検討するとして、⑤-1~3が具体的に述べられ、物語らしい構成になっている。延慶本と比較すると、この⑤の増補要素が少なく、5つの基本要素に対して比較的忠実な展開をしている本だと言える。しかし、私は平家物語がこの5要素でもって始まったと言っているのではない。平家物語は相当に高度な宗教的・政治的目的を持って語り始められた作品であり、成立当初から複雑な構成要素を持っていたと考えるからである。編纂当時、おそらくこの5つの要素を含む「山門の強訴・師通たたり死に事件」の物語が世間に流布しており、平家物語に取り込むに当たっては、その基本要素に付加要素を加えて編纂したものと考えられる。諸本によって付加要素が異なるのはその編纂意図が異なるからではないかと考えている。 |
*Ⅵ-1:山下宏明「平家物語の生成」
|
|
2.法華問答講開催による三年の延命
延慶本と四部本を比較してゆくことで、延慶本の抱える課題を考えてみたい。右の比較表ボタンを押して比較表を見ていただきたい。なほ表の左端の番号は「Ⅰ八王子の麓にて 3.「願立」を読む」に付した番号である。 (1)ではの延慶本の事件年号だけが嘉保一年で、四部本は嘉応二年(嘉保の誤記か)と異なっているが、諸本はほぼ同じ内容で、史実とは異なり、強訴を正当化する山門寄りの記事となっている。 『(師通の死は)四十才にも届かないで、惜しまれる御齢であった。限りある命とは云うものの、腫物に関する人の噂は、常のことと云いながら、山の大衆のおどろおどろしく言うのも厭わしく、世の中にも不快な心が積もりかねないと申しております。』 強訴事件の直後にはたたりは発生しなかった。それから2年も経った永長二年に師通が亡くなるが、その死後、幾ばくも立たぬうちから、山門の大衆により「それ見たことか」という風に、たたりの風説が流されたことが伺える記事である。大衆呪詛から時間を置き、たたり発生からまもなく師通が死去するという時間配分を見せる四部本の構成の方が三年延命という構成の延慶本より史実に近いと云うことができるだろう。山門側は天皇と共に行った師通の「天下粛然」と評価された政策を目の上のたんこぶと思っていた。死去をきっかけに、その死が山王権現のたたりだという噂を流し、山王権現の恐ろしさを宣伝し、恐怖心を軸として民意を引き付けようと目論んだのであろう。しかし今鏡の作者(寂超といわれている)は山門の流す風説を「おどろおどろしく言う」と批判し、「世の中にも不快な心が積もりかねない」と嘆いている。当時から山門の言動は穏当さを欠いていると心ある人々からは見られていたのであるが、山門側に立って編纂された平家物語は、山門が流した「師通たたり死」という風説に寄り添い、バイアスのかかった物語を展開する。 延慶本は、まず呪詛後、直ちにたたりが発生したと書くことで、強いインパクトを読者に与え、さらに三年ほどの隔たりがある呪詛から師通死亡までの時間を利用して、立願の中に法華問答講を挟み込み、三年の延命が叶ったという形を整えたものと考えられる。延慶本が「法華問答講」を抱え込んだことにより、そもそもの「願立」の物語の諸要素が、単なる神輿動座のエピソードから山王のたたりの恐ろしさの物語へ大きく変化したのである。延慶本記事は「八王子」という場所の記述で徹底しているが、その背景には、水原一氏が指摘されるように、「願立」という説話を八王子における法華問答講の物語に置き換えるための意図的な改編が行われたのではないだろうか。改編部分を個別に見てゆく。
|
*Ⅵ-2:名波弘彰「師通願立説話と日吉神 |
|
3.「願立」の場
まず表Ⅵ-1の(2) では、四部本(他本も)では射殺された禰宜のことを記述しないか、記述しても「禰宜友実」とするだけであるのに対し、延慶本では所属を「八王子の禰宜友実」と記述する。日吉社の神官系図によれば禰宜が所属するのは西本宮と東本宮だけであり、八王子に禰宜はいない。友実は山王権現(大宮)の第十四代の禰宜である。八王子の禰宜という設定は延慶本編纂者の誤解か、八王子を強調するための改ざんと考えられる。 (3) では四部本が「根本中堂に神輿を振り上げて呪詛」と記すのに対し、延慶本は「神輿を中堂へ振上げ奉り、禰宜をば八王子の拝殿に舁き入れて、静信、定学二人を以て、関白殿を咒咀し奉る。」と記述し、呪詛の場所が根本中堂なのか八王子なのか、あるいは両方の場所なのか、フォーカスがぼけることを無視して「八王子」を持ち込んでいる。 つぎに
(5)
では延慶本が「八王子より鏑矢が発射されるのを人々が夢に見る」と記述しているが、四部本には鏑矢発射の記事はない。四部本では山王のたたりは二年たってから顕れるので、直ちにたたり顕現を強調する「鏑矢の発射」の記述を必要としない。延慶本他は「法華問答講による三年延命」という要素を用意したことに連動して、大衆が呪詛し、山王が直ちにたたりを発生させることが可能となり、「鏑矢の発射」を持ち込んだのである。そうすることで、「願立」を大衆が頼めば山王は直ぐに答えて下さるという強いインパクトを持った恫喝の物語に改編したのである。それ故、(9)における物語の結論を、延慶本は「昔も今も山王の御威光は恐るべき事とぞ申伝たる」と諸本とは異なる結論を記述することが可能となったのである。 四部本他諸本の結論は「昔も今も、山門の訴訟は怖しき事なりとぞ申し伝へたる」と書かれている。「願立」というエピソードが神輿の動座という言葉に触発されて挿入されたものであることを考えると、四部本の「山門の訴訟は怖しき事」という結論が本来の趣旨に添うものであるが、延慶本は「山王の御威光」に改編したものであり、山門から山王へ軸をずらし、八王子の法華問答講を際立たせようとした延長にある結論と言えるだろう。 (6)では
延慶本は参籠の冒頭「北の政所は日吉の社に」と参籠場所を日吉の社とだけ記するが、(7)-1で「不思議なことに、八王子の社にはたくさんの人々が参籠していたが、陸奥よりはるばるやってきた童御子が夜半ごろ、にわかに息絶えたのである。社殿より遠く離れたところへかき出し、祈っていると、程なく生き返り、立ち上がって舞を舞いはじめたので、人々は奇特な思いにとらわれてこれを見守った。」と記されており、八王子に参籠した童神子に山王が憑依託宣するのを北の政所が目撃する設定となっているので、場所が八王子境内と推測可能である。それに対し、四部本は十禅師境内である。また延慶本では童御子に憑依するのは山王権現であり、四部本では十禅師と設定されている。 現地をよく知っておられる方ならご理解いただけると思うが、八王子権現の場所は、牛尾山の急峻な傾斜地上にあり、建築の様式は清水寺の舞台と同じ懸崖造りで、金大巌の下の崖にへばり付くように建てられている。かき出した死体が、蘇生して舞を舞ったり、それを大勢の参籠者が取り囲んで見物するような平らな空間などほとんどない。そうした空間を確保するためには下山して、二宮の境内付近まで戻るしかない。延慶本もそのことを考慮して『遙にかき出して』と記したのかもしれない。それならやはり山麓の十禪師境内付近まで担いで降りたことになる。 (7)-2の第一願を延慶本は『八王子の社より此砌まで廻廊作て』と記すが、それは託宣が行われている場所が「此砌」であり八王子境内でないことを示している。長門本では北の政所の心中の願が「八王子の御前より十ぜんじの御前まで廻廊を造て」と事前に語られ、その後、山王が憑依した童神子が「八王寺の社より此砌まで廻廊を立て」と同じ内容を繰り返す。同じ場所の繰り返しであるため、「十ぜんし」という部分を「此砌」と端折ったのである。延慶本の記述はこの端折りの部分の残欠と考えられ、もともとが十禅師を舞台としていた物語を「法華問答講」に塗り替えるため八王子境内の物語に改編した時に、塗り残した部分を示している。 (7)-5 「娘による芝田楽奉納」は延慶本・覚一本・長門本・盛衰記などの鏑矢・法華問答講・三年延命の記事を掲載する諸本が記しており、これらの記事と一つながりの関係にあるものである。田楽は八王子信仰と密接に結びついている。「耀天記」八王子の事には山王権現が降臨の時、八王子権現が饗応した記事が掲載されている。 『成仲總官禰宜の説に言う、この場所へ大宮(山王権現)が初めて降臨されたとき、八王子の峯より八人の童子形の神が鬢鬘を結い、降臨して、田楽で大宮を饗応した。それより田楽の本座は、八王子の御輿の御共で御祭の時も伺候することとなった。その八人の童子形の者は、この山の神であった。』 本記事は八王子権現が、山王権現の始めての日吉降臨の時に田楽で饗応したという、八王子権現を本拠地として活躍する田楽本座の縁起譚である。田楽は現在の山王祭でも宵宮落としの時に演じられ、伝統を伝えている。芝田楽の立願は、この八王子に付属する田楽の本座が関与して、八王子関連記事に紛れて挿入されたものであろう。 以上の通り、四部本との比較において延慶本は、「八王子の法華問答講」というキーワードで意図的に統一された物語であることがご理解いただけたことと思う。おそらく山門の風説を元とした「願立」のプロトタイプが存在し、そのプロトタイプに「八王子における法華問答講」が持ち込まれる形で、延慶本の祖本が編纂されたものと考える。四部本の祖本は「八王子における法華問答講」に影響されず、元のプロトタイプに近いまま編集された本である。 長門本・盛衰記との直接的比較は煩瑣を避けるため省いた。長門本で(3)における山門大衆の呪詛の場所を、根本中堂としながら、時間差を置いて八王子でも行い、盛衰記でも、八王子で呪詛した結果、鏑矢が飛び出したので、根本中堂に神輿を担ぎ上げ呪詛したと書かれており、両場所を記述する延慶本と通じるものがある。また、長門本・盛衰記は一方では四部本と同様に「願立」の行われた場所を十禅師としながら、他方では延慶本と同様の鏑矢・法華問答講・三年延命の記述があり、両方の要素を備えている。もともと両本は多様な挿話や要素を抱え込む傾向が強い本であるから、プロトタイプの十禅師境内に法華問答講が継ぎ合わされるような形で両方の要素が抱え込まれたものと考える。もちろん「山門の訴訟は怖しき事」という文末の結論も四部本的要素の残滓である。 |
*Ⅵ-5:名波弘彰「師通願立説話と日吉神
|
| 4.十禅師=憑依託宣する神
北の政所の参籠の場所が、延慶本では八王子権現の境内となっているのは「八王子における法華問答講開催」とい要素を物語に持ち込むための意図的な改編であった。そのことは「この砌まで」という記述が、「じゅうぜんし権現まで」を略述した文であることを長門本により証明した。また延慶本は「陸奥よりやってきた童神子に憑依し託宣するのは山王権現」という設定になっている。それに対して四部合戦状本・長門本・源平盛衰記では、関白の母上が七日間参籠したのは十禅師の境内であり、出羽の童神子に憑依し、託宣を行ったのも十禅師権現
(長門本は山王権現)
とし、延慶本や覚一本と異なっている。私は平家物語に持ち込まれる以前の「願立」は十禅師権現境内という場所の設定がされていた物語だったものと思う。その形に近い構造を示しているが四部本のような物語であったことを述べた。四部合戦状本や源平盛衰記が「願立」の舞台を十禪師とし、憑依託宣したのが十禅師であったことには一定の根拠があると私は考えている。その理由は、当時の山王信仰において十禅師が際だった特徴を持っているからである。山王絵詞(第八巻 四話)には次のような話がある。 『東塔の源恵法印は毎年欠かさず六箇日、聖真子に対する不断念仏を勤めた。それは次の理由からである。彼が日吉の社頭に二百ヶ日参籠して、年来切望していた(延命という)願い事を祈った。山王権現のご意向をお諮りするため、姫座の寄琴を使って十禪師を勧請した。すぐにご託宣が下った。法印が云う「私の祈請に御感応して頂けたでしょうか。どうにかして命を延ばし、後世菩提のお勤めをさせてください。」十禅師が申されるには「定業は前世から定まっていることで変えることが出来ない。私の力が及ぶことではない。但し、決定した悪業を転じ、浄土にも往生し、福も来、命を延ばすために、聖眞子の不断念仏がある。汝はそれを懃めるべきである」云々。それ故、彼の法印は毎年六箇日、世におられる間お勤めになった。(略)』 東塔の源恵法印は山王権現のご意向をお諮りするため十禪師を勧請する。ここでは山王権現のメッセンジャーである十禪師が姫座の寄琴という巫女に憑依して、山王権現の言葉を伝える。日吉境内おいて山王権現のご意向をどのようにして伺ったかが明示されている。 十禪師は上七社の間でも山王権現のエージェントという特殊な位置を独占し、女・子供・巫女に憑依して山王権現の意向を託宣する神と信じられていた。山王権現の霊験・利生譚を集めた山王利生記・山王絵詞には七十程の神仏が登場する説話が含まれているが、その内十七話に十禪師が登場する。これは山王権現(大宮という表記を含む)の五十三話についで多く、二宮の五話、聖真子の三話などと比べ他を圧倒している。山王権現信仰圏の中で十禪師は特異なポジションを占めていたのである。利生記のなかで、十禪師は人の夢の中に示現し、女・子供に憑依し、山王権現の代理者として託宣を行う。十禅師はよく山王権現の意向を語る神と信じられていたのである。憑依託宣はほぼ十禪師の専権事項であった。次節で述べるような背景のもとに、十禪師=憑依託宣の神という信仰が天台信仰圏全体に広がっており、憑依託宣するなら十禪師がやるだろうという共通認識があった。「願立」のもととなった説話段階では、説話の舞台が当然のこととして十禪師に設定されていたと考えるのである。十禅師の託宣は山王のエージェントとしての託宣であった。四部本他の十禅師の託宣も同様にとらえることが出来る。長門本における託宣する神が山王権現とするのも、つねに十禅師の託宣の背景に常に山王権現がいることを思うと、不自然なことではない。 |
*Ⅵ-8:佐藤眞人「中世日吉の巫覡につい
*Ⅵ-9:下坂守「描かれた日本の中世」
|
| 5.十禪師縁起
十禪師権現の信仰背景をもう少し掘り下げてみたい。十禅師権現は現在では樹下社と呼ばれ、東本宮系の一社で、八王子山の山麓の東本宮系の社殿が集合する境内の一角に鎮座する。大社のホームペジでは祭神は鴨玉依とされている。これは「日吉禰宜口伝抄」の次の記述を根拠としているものと思われる。 『小比叡(二宮)の別宮は三座である。鴨玉依姫神、玉依彦神、別雷神の三柱が坐す。その別宮は樹下宮とも言い、又十禅師宮とも言う。この十禅師宮という名は、寶亀年中(770~781)に内供奉十禪師であった延秀が香積寺に於いて、神託を蒙り、小比叡別宮を造り、本宮の玉依姫、玉依彦、別雷神三座を御遷座申し上げた事にもとづく。・・・中略・・・又伝承では、賀茂中社に田があり、主に苗を植えていた。ある時、苗がにわかに槻木(けやき)に変じ、玉依姫はこの樹下で神となられた。その故に樹下宮と言う。』 内供部とは朝廷で読経をあげるため選ばれた僧侶のことであり、十禅師とは霊力の強い十の僧侶という意味である。十禅師の名はその内供奉十禪師の延秀という僧に由来すること、賀茂神社の槻木の下で下賀茂神社の祭神玉依姫が神となられたことにより樹下宮の名が付けられたとする名前の由来譚が語られる。「日吉禰宜口伝抄」は永承二年(1047)の日付が記されているが、実は近世の偽書と云われている。賀茂神社の神主の家系である祝部家が十禅師=鴨玉依姫・玉依彦・別雷神の賀茂系祭神を持ち込むため編纂したもののようである。しかしすべてが虚構ではなく、伝承された家の記録が反映している部分も存在する。内供奉十禪師延秀という人物は寶亀三年(772)の「続日本紀」に登場する実在の十禅師であり、彼のことを記した祝部家の伝承が記家(山門の記録僧)の手になる山王神道の理論書「耀天記」に採録されている。 『(祝部)成仲の説に云う、中古横川の香積寺の十人の供僧の中に、一人智行兼備の高徳の人がおり、十禅師の中の一人であった、現身に山王権現と言葉を交わせる人であった。荒人神となられた。それ故、十禅師と申しあげる』 祝部成仲は十二世紀の院政期の日吉社の神主で、大宮縁起の賀茂系の松尾の神との同体説を持ち込んだ人物と見られるが、ここでは祭神鴨玉依姫の名は記されていない。香積寺の十禅師というのは、延秀と同一人物であろう。延秀は常人では聞くことが出来ない山王権現の言葉を聞き、言葉を交わすことが出来る異能の人であった。彼は死して荒人神(=現人神)となり、祀られた、それ故、その荒人神を十禪師と申し上げるというのである。香積寺の十禅師が神と言葉を交わす異能者であったことに注意をしておこう。 さて山門側では十禪師をどのように見ていたのであろうか。同じく記家による山王神道の書「山家要記浅略」は最澄入山時のすさまじい光景を描き、最澄が山王権現に先立って十禪師に邂逅したことを記している。 『二十四日、最澄は北の山林に行き、一人の霊童に遭遇する。最澄が「どなたですか」と問う。霊童が答える「われは天地経緯(開闢以来)の霊童である。衆生とは生まれながらに運命を共にする神である。一つに(十禪師)という名である。功徳は限りなく広大で、我は無尽の願いを誓う。願うところはことごとく成就する。」大師が云う「十禪師に帰依申し上げます。この地を清浄寂光の地となし、日頃の起居動作総てから煩悩の炎を断ち切って下さい。」霊童が重ねて示して云う。「樹下の和光同塵は二度行われた。そのことはすでに成就している。このたび我が宝前に詣でない者は、何者であっても輪廻転生の苦から遁れられないものと知りなさい。」 二十六日、最澄が東の高い峰を越え、切り立った巌の上に佇んだとき、一人の化人が現れた。(略)大師が名を問うと「我は山王である。日域の冥神である。」と答えた。(略)』 霊童姿の十禪師は「樹下の和光同塵は二度行われた。」という神の言葉を伝えた。これは釈迦を本地とし、山王権現を垂迹とする山王神道の根本教義にもとづいている。すなわち菩提樹の下で釈迦が悟りを開いたことが一度目の和光同塵であり、日吉の樹下で山王権現が垂迹したことが二度目の和光同塵とする考え方である。このことはすでに実現しているとして、翌々日の山王権現との邂逅を預言した託宣なのである。「山家要略記」の十禪師大明神垂迹事では「伝教大師は山王権現と十禪師の像を自ら造り、根本中堂の鎮守とした」ことが記されており、中世初頭の段階で十禪師は日本天台創始神話に割り込みをはかり、その信仰は「一児二山王」と云われるほどに成長し、託宣する童子神としてのイメージを定着させていたのである。山王曼荼羅の十禪師は通常、地蔵菩薩の姿か若い像の姿で描かれる。しかしそれとは別に十禪師を童子形で描がくものがあるが、それはこうした霊童の神話を反映したものであろう。十禪師が児童形で形象されたことは重要で、陰陽道との相互影響で成長しつつあった護法童子信仰と習合し、ますます憑依託宣する神のイメージを強化させたものと考える。護法童子は阿部清明など陰陽師が使役した鬼のような形相をした式神が仏教に取り入れられて発達したもので、仏教を守護する神仏や有能な験者の手助けをする童形の神であった。役小角配下の鬼神衆や、白山の泰澄に仕えた臥行者、不動明王の矜羯羅童子・勢多迦童子等の他、信貴山縁起絵巻に描かれた剣の護法童子は信貴山の命蓮の代理で、醍醐帝の病を治療する姿が描かれる。日吉山王利生記ではおさない童姿の十禪師が描かれる。 『侍従大納言成通卿がご病気になり、湛秀巳講が大般若経を読んで祈った。病は日増しに重くなるので、願を立てるため巳講を近くにお呼びになり、話し合っていると、おさない童が三尺の几帳を踊り超え巳講の前に立った。驚き怪しんでいる巳講に「我は十禪師である。不浄事があるので、それを咎めておる。」と云う。巳講が「諸法師には不浄なしと云います。何の経典に物忌みせよと書かれているのですか。」と反論すると童は「出離生死は聖教の大綱である。しかるに愚かな衆生が生死を軽んじるのを見て憎く思うのである。衆生を導くために垂迹したのであるが、なお生死を忌めと強く誡めるのである。」と見事に聖教の道理を説いてみせた。巳講は自らの至らなさに涙を流して詫び、直ちに物忌みに入ることを誓った。十禪師は巳講を許し、寝入るがごとくに神上がりなさった。神慮はまことにはかりがたいことである。』(日吉山王利生記巻六の三段概略) 不浄事があるので、物忌みせよと命ずる十禪師に対し、巳講はその姿が童子形故に怪しみ、何故物忌みをしなければならないのか、どのお経にそのように書かれているのかと問う。童子は聖教の理りを説き、巳講を目覚めさせる。幼い童子姿の十禪師が几帳を踊り超えるイメージは鮮烈である。童姿の十禪師はまさしく山王権現の代理を務め、山王の言葉を伝える護法童子として描かれている。 以上の検討から、十禪師が山王権現のメッセンジャーであり、山王権現の意向を伝える神であると信じられていた平家物語編纂時代の山王・山門信仰圏における状況がいかなるものであったかお分かり頂けたものと思う。四部本・長門本・盛衰記が憑依託宣の場所を十禅師権現の境内としたのは、そうした日吉社の信仰環境を反映したものであった。 |
|